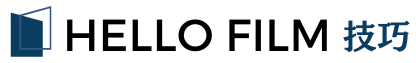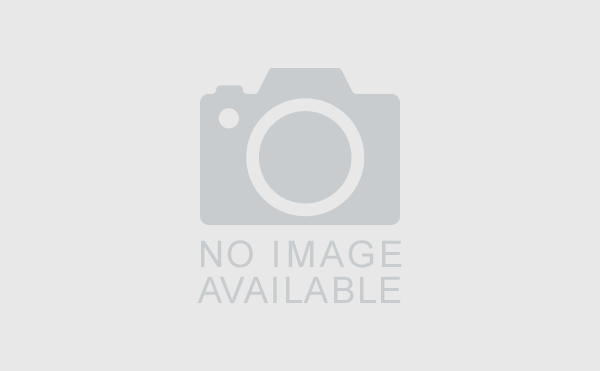【便利屋】とは…
便利屋(べんりや)は万屋(よろずや)「なんでも屋」などともよばれ、 様々な雑事の代行業務を行うサービス業者です。
特に、法律及び行政で規定された公的資格いりませんが、 業務内容により公的資格を取得する必要とするものもあります。
Wikipediaではこのように表記されています。
弊社は「窓ガラスフィルム施工」&「ガラスコーティング施工」&「専門清掃」をメイン事業としてスタートしましたが、この中のいずれかをきっかけに地域の皆様とのつながりが増えていく中、いろいろなお悩みやご相談を受けることが多くなっていきました。「便利屋」というと作業範囲やしごとの括りが不明瞭で、定義があるのか調べてみたところ、この様な感じでした。こうなると弊社も「便利屋」と言えなくもない、少なくても間違ってはいないようです。世間的に「便利屋」のほうが分かりやすいとすれば、屋号の隣にショルダーネームとして「便利屋」とつけたほうが良いのかも‥と思うようになってきた今日この頃、少しホームページにも「便利屋」のワードを入れてみました。
正直なことを言うと、このようなお悩みやご相談にすべて完璧にお答えできているわけではありません。しかし、このようなご相談を頂けるという事は、お客様から”一定の信頼を頂けた証”とうれしく感じています。そのため毎回「ありがとうございます」という感謝の気持ちでご応対させて頂いているのです。
一つのご依頼で初めてお会いするお客様と施工完了までに何度かやり取りをしただけでは人として信用などしてもらえない世の中だと思っています。詐欺の手口は様々で年々巧妙になってきています。悪質なリフォーム業者も何十年も前から堪えません。知らない人を家の中に入れるという事は怖い世の中になっています。そんな中、たった一度、たった一つの施工のつながりで私にいろいろなお悩みやご相談をしていただけるという事は本当にとても嬉しいことです。
商売をしていく以上、利益は重要です。「リンゴ1個100円」のように値段や料金が分かりずらい業種(特にリフォーム業はそれにあたりますよね‥)は利益ばかりにフォーカスしていると詐欺と堺が見分けづらくなります。だからこそ仕事に対する姿勢やお客様との接し方、経営方針など含め、安心していただけるよう振舞うことが大切だと思っています。私はこれからもできるだけ私なりの《GIVER/ギバーの精神》「お客様にいただく物 < それ以上をお返しする」でみなさまとの繋がりを大事にしていきたいと思っております。
※以下に消費者庁、国民共済等のホームページから抜粋した記事を載せています、合わせてご覧になっていただけたらと思います。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!
いきなり「無料診断やってます」と訪問してきて、「異常がある」と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意しましょう。訪問販売などで悪質な住宅リフォーム業者と契約をしてしまった場合、契約書面を受け取った日から原則8日間以内に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
このほか、不要なリフォームを契約してしまった場合などは一人で悩まず、消費者ホットライン188や住まいるダイヤルにご相談ください。
住宅・屋根修理の詐欺・悪徳商法にご注意を!
飛び込み営業や保険・共済を利用した手口とその対策
“住宅修理に関わる悪質な商法”の現状
住宅修理業界において悪質な商法が横行していることが問題となっています。特に台風や大雨の後に、悪質な業者が被災した方を狙う傾向が確認されています。
これらの悪質業者は、飛び込み訪問をして、屋根修理等を勧める手法を使用しています。何も知らずにそのまま契約をしてしまうと、高額な修理費用を請求されたり、不当な手数料を払わされたりする可能性があります。
悪質業者から身を守るためには、慎重にリサーチし、本当に必要な修理か、発注先として最適か、などを確認することが重要です。
トラブル増加を受け国土交通省が注意喚起
相談件数は増加傾向
最近は、特に「火災保険・火災共済を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金・共済金が出るようサポートする」など、「保険金・共済金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。
国民生活センターの統計【グラフ1】によると夏の豪雨や冬の豪雪被害が多くみられた2020年度の相談件数は前年度の2倍近くに膨れ上がりました。
こうした状況を受け、国土交通省は『災害に便乗した悪質リフォームに関する注意喚起について』と題する文書を発表。
これまでも関係省庁などとの連名でチラシ【図1】を作成し注意喚起をしてきたものの、トラブルが無くならないため、住宅関係団体や都道府県などの担当部局に対して注意喚起と協力を依頼しました。
自身やご家族、周りの方の被害を防ぐためには、私たち一人ひとりが注意し、周りの方に注意をよびかけることも重要です。
住宅修理・屋根修理の悪質な事例
実際に悪質業者と接触した具体的な事例をいくつかご紹介します。
事例①強引に話を進める悪質業者
ある日、Aさんの元に修理業者から電話。「ご自宅の屋根が台風の被害で壊れています」「保険を使えば修理することができます」と説明され、後日自宅に来てもらうことになりました。
訪問当日、業者は屋根の状況を確認すると「すぐに共済に電話をしてください」とまくしたて、Aさんは言われるがまま電話。業者の指示のもと、共済金の請求手続きを進めることに。
後日、Aさんの元に修理の見積もりが届きました。そこには、想定を大きく超えた金額が。さらに業者は、共済金の支払いが確定する前にも関わらず、支払われる前提で契約を結ぶよう迫りました。Aさんは戸惑いながらも、早く自宅を修理したい思いから、契約を交わしてしまいました。 その後、Aさんからこくみん共済 coop に相談し、「悪質な業者の可能性がある」と気づいたAさんはクーリングオフの手続きを行うことになりました。

悪質なケースでは、経年劣化の部分を「台風の被害だ」と偽って話を進めようとしたり、 調査の際に業者によって意図的に破壊されたと疑われる痕跡があった事例もあります。
また、工事をキャンセルしても、違約金を口実に金銭を要求する業者も確認されています。
事例②インターネットに潜む悪質業者
自宅の屋根が台風の影響で壊れていることに気が付いたBさん。家を建てた工務店はすでに廃業していたため、インターネットで修理業者を検索したところ、「家の補修には保険が使える」と大きく謳っている業者を発見。ホームページもわかりやすく信頼できると感じ、すぐに連絡を取りました。
後日、修理業者が自宅を訪問し、破損個所や状況を確認。親身に話を聞いてくれたことで安心し、修理と共済金の手続きを進めました。
しかし、実際に届いた見積もりは想定を超える高額なものでした。
インターネット上には、悪質業者も多く潜んでいます。ひと昔前は口コミサイトやSNSで信頼性を確認できましたが、最近ではそれすらも疑わしい情報が増えています。特にリフォームや修理の依頼は慎重に行う必要があります。信頼できる業者を見極めるためには、複数の見積もりを比較し、口コミや評判を慎重に確認することが重要です。

「火災保険の申請を代行します」などと大きく謳っている業者に依頼せず、まずは、ご自身で契約されている共済団体や保険会社に連絡しましょう。
悪質業者・詐欺被害から身を守るための対策
悪質なリフォーム詐欺の被害から身を守るために何ができるでしょうか? 対策を4点ご紹介します。
対策1:アポイントがない訪問は疑う!
悪質な業者はアポイントなしで訪問してくるケースが多く見られます。
また、診断や点検を勝手に始めようとしたり、その場で無理な契約を迫ったりすることがあります。
強引に話を進めようとする業者に対しては毅然とした態度で断るようにしましょう。
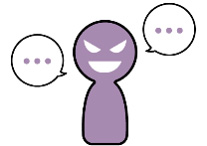
対策2:契約している共済団体や保険会社には自分で連絡する
住宅保障を契約している共済団体や保険会社に自分で連絡し、突然の訪問による提案を受けている事実や自身で請求する場合の流れについて相談しましょう。

対策3:業者の住所を確認!
必ず名刺を受け取り、業者の住所などを確認してみましょう。
悪質な業者は、該当の住所に別の企業が入っていたり、建物自体が存在していないことがあります。
怪しい住所や連絡先を持つ業者には注意しましょう。
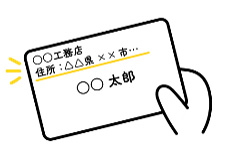
対策4:地元の複数の業者に見積もりを依頼!
地域で顔が見える業者・工務店に相見積もりをお願いするようにしましょう。複数の業者に見積もりをお願いすることで、修理の相場がわかります。
相場が妥当で、実績がある地元の優良業者に依頼することで、安心して工事を進めることができます。

まとめ
この記事では“住宅修理に関わる悪質な商法”による被害を避けるための対処法についてご紹介しました。悪質業者や詐欺被害から身を守るためには、冷静な判断と情報収集が欠かせません。
どんな時でも、焦らず、その場で一人で決めないようにすることが大切です。ご家族やご近所同士などで相談をするように心がけましょう。
※こくみん共済のオフィシャルサイトより抜粋